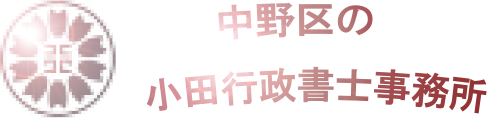特定技能1号(トラック運転手)の手続きの流れ
まず要件確認、次に支援計画、そして入管申請。だから、混乱せず確実に進められます。
全体の流れ(まず全体像から)
トラック運転手として外国人材を特定技能1号で受け入れるには、複数の手続きが関係します。つまり、「採用 → 支援体制 → 入管申請 → 就労開始」という流れを順序よく進めることがポイントです。以下では、実際の現場に即した流れをわかりやすく整理しました。
① 要件確認と採用計画の整理
まず最初に、会社が「特定技能所属機関」としての要件を満たしているかを確認します。加えて、受け入れ予定の外国人が技能試験・日本語試験を合格しているかもチェックします。
- 事業内容が自動車運送業分野に該当しているか
- 労働条件・賃金が日本人と同等以上か
- 支援体制(生活支援・相談担当者など)が確保できるか
- 受け入れ予定者が技能測定試験・日本語試験に合格しているか
つまり、最初の段階で「できる/できない」を整理しておくことが、後のトラブル防止につながります。
② 支援計画書の作成と社内体制づくり
次に、受入企業が作成する支援計画書を整えます。これは、外国人が安心して働き、生活できるようにするための具体的な計画書です。さらに、社内の担当者や協力先(登録支援機関など)を決定します。
- 支援計画書の作成(生活指導・相談対応・日本語学習支援など)
- 労使協定・就業規則など社内文書の整備
- 支援責任者・連絡担当者の任命
- 外部登録支援機関との契約(必要な場合)
こうした下準備が整えば、あとは入管申請に進むだけです。言い換えれば、ここでの「設計図づくり」が成功の分かれ目です。
③ 必要書類の準備と確認(代表例です。国籍や受け入れ企業規模等で必要書類は変化します。)
つづいて、申請に必要な書類をそろえます。なお、提出書類は企業側・本人側・支援機関側の3方向にまたがるため、チェックリストを活用して順番に整えるのがポイントです。
- 雇用契約書(日本人と同等以上の待遇)
- 会社登記事項証明書・直近の決算書
- 技能試験・日本語試験の合格証明書
- 支援計画書・労使協定
- 本人のパスポート・在留カード(該当時)
行政書士が内容を精査し、さらに不備があれば即座に修正します。結果として、補正通知を防ぎ、審査期間を短縮できます。
④ 在留資格認定・変更申請
すべての準備が整ったら、いよいよ入管申請です。新規採用の場合は「在留資格認定証明書交付申請」、すでに在留している場合は「在留資格変更許可申請」を行います。
- 申請書類一式を入管へ提出(地方出入国在留管理局)
- 補正・照会対応(行政書士が代理)
- 結果通知(許可証の受領)
つまり、申請は「提出して終わり」ではなく、照会・補正への即応力が求められます。だからこそ、専門家の伴走が安心です。
⑤ 入国・就労開始・定着支援
許可後は、入国(または変更後の在留カード交付)を経て、正式に就労が始まります。同時に、支援計画に基づく生活支援・日本語学習・面談記録などを実施します。
- 住居・口座・保険・携帯電話などの生活サポート
- 入社・安全運転研修・日本語指導
- 定期面談・記録保存(出入国庁への届出含む)
この「定着支援」こそ、特定技能制度の要です。言い換えれば、雇用継続と安心がここで生まれます。
まとめ:だから順序が大切です
採用を急ぐあまり、手続きを逆順に進めると、結果的に再申請や不許可につながることもあります。だからこそ、まず全体像を押さえ、つぎに順番を守る。そして、行政書士が横でチェックする。この流れが一番確実です。